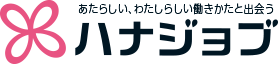大学卒業後、教育系の出版社、そして島根県海士町の公営塾で働いていた的場陽子さん。29才で憧れていた海外留学!留学先はデンマークです。海外での暮らしや学びをデンマークからお届けします!学生時代に留学するかどうか迷っているというみなさん、社会人になってからの留学を選択肢に入れてみては?(過去の記事はこちら→『立ちどまれるって素晴らしい!私が日本から離れてデンマークに行った理由』)
ホイスコーレの朝礼時に校長のElse(エルサ)が、他の先生たちが度々口にしていたことがあります。
それは、“Live together”、“Focus on yourself ” 、“Democracy”の3つでした。これらの3つこそが、ホイスコーレの本質と言える概念です。
しかし私は、在学中にこれらの言葉が示している意味を理解できてはいなかったのだと、卒業して半年経った今思います。
厳密に言うと、言葉では理解していたのですが、それが実体験として、温度を持って自分の中に根付くのに時間がかかったというのでしょうか。
第1回で紹介したホイスコーレの持つ特徴(「試験がない」「全寮制である」「17歳以上ならば誰でもいつでも通うことができる」)はすべてこれら3つの要素を実現するために機能していたということも、卒業後に気づきました。
この3つの要素を1つずつ、ホイスコーレでの体験と共に紐解いて行きたいと思います。

Live together -他者と共に生きる
ホイスコーレの生活は思ったよりも盛りだくさんだった、ということは以前にも少し触れました。
朝起きてから夜寝るまで、1日3回の食事、掃除、朝礼、授業といった基本的なスケジュールはすべて生徒と先生の共同作業になります。夕食が終わったあとにも、生徒が企画したイベントがあったり、コモンルームで皆がバラバラなことをしながらも、場所を共にする時間があったり。部屋も1人部屋は選べますが、多くは2人部屋のつくりになっています。
この生活スタイルは、社会人になってからずっと1人暮らしだった私にとって、慣れるまで時間がかかりました。
ルームメイトとの相性はとても良く、彼女以上の相手はいなかったのではないか、と思うほどでしたが、完全に1人になる時間が限られているというのは、それでもストレスが溜まるものでした。
しかし、今思うとこの共同生活がベースにあったからこそ、他者と共に生活をするということはどういうことなのか、に気づくことができたのだと思います。
Focus on yourself -自分に焦点を当てる
当たり前のことですが、毎日の調子には山谷があります。
その日の天候によって体調が左右されたり、月曜日と金曜日でも疲労感が異なったり。私は自分が思っていた以上に、体調によって心の余裕が左右される人間なのだということに、仕事を離れたホイスコーレでの生活で気づきました。
東京でも海士町でも、仕事を中心に生活スタイルを確立していたので、睡眠時間は常時6時間ほど。食事も自分の体が食べたいものを食べたい分というよりは、ストレス解消のために食べることもあったと思います。
私は睡眠時間が7時間でも足りないぐらいで、実質8時間とらないと体調と頭の回転を一番いい状態で維持できませんでした。
そして、食べ過ぎる時は大概頭でなにかを考え過ぎていて、それらから逃げたい時。翌日が雨の予報の時は、前日の夜からかなり強めの頭痛が起こりやすい。生理前は日中でも強い眠気が襲ってきて、朝が起きられない・・・など、今まで自分の体のシグナルにいかに無頓着だったのか、に次第に気づくようになったのです。
自分を見せることが気遣いになる
そのように自分の体調のクセに気づくと、体調と心が連動していることも分かってきました。
自分から話しかけよう、と思えるのは体調がいい時。ちょっと今日は聞き役になろうかな、と思うときは体調がすぐれない時。
そしてルームメイトのNanna(ナンナ)には、自分の体調がすぐれない時は努めて伝えるようにしました。
今まで私は、「体調管理ができていない=自分の管理能力が足りていない」と公言するようで、あまり職場などで自分から積極的に伝えていなかったように思います。
けれども、Nannaやよく接する友人たちと良好な関係を築く上で、自分が今どのような状態にいるのか、今日はどんな環境に居たいのか、を伝えることはとても大切なのだ、と身を持って知りました。
自分から伝えることで相手に必要以上に気を遣わせることがなく、また自分の状況を察して欲しいという期待をせずに済むということを知れたのは、とても大きなことでした。
察して欲しい、という待ちの姿勢を変えることは、相手に合わせようしてきていた習性からの脱却にもなりました。
一番顕著に変わったのは、母親とのコミュニケーション。Skypeをする時、まず母に、今自分が体調も含めどのような状況にあるのか、どんな気持ちなのか、をきちんと言葉にして伝える。
それだけで、母親の望む受け答えをするのではなく、自分がどのような関係性で、どんな話をしたいと思っているのか、が自分でも少しずつ俯瞰できるようになったのです。母親の発言に傷ついたり、腹が立ったりした時は、我慢するのではなく、できるだけきちんとその時感じた気持ちをそのまま伝えるようにしました。
今までヒステリックになって自己嫌悪に陥っていた時を思うと、自分の中に生まれた感情をきちんと扱うことができる、というだけでこんなにも穏やかになれるのか、とびっくりしたぐらいでした。
選ぶということ
ホイスコーレでは毎週末にパーティーがあります。
パーティーコミュニティ(希望者による委員会のようなもの)が考えてくれたテーマにそってみんながドレスアップする、意外に手の込んだものでした。
Assemblyroomには装飾が施され、テーマに合った音楽がかかり、バーコミュニティによるバーが開かれ、朝方まで踊ったり飲んだり(時には飲みゲームも)。

最初は物珍しく、積極的に参加していたパーティーでしたが、私は元々騒がしい場がそこまで好きなタイプの人間ではないので、次第に週末が憂鬱になってきました。
あくまでパーティーは自由参加である、ということはわかっていながらも、“企画してくれている生徒たちに悪いかな”とか、“自分だけ共有できないなにかがあると寂しいしなぁ”、色々な思いが駆け巡り、パーティーに出ないという選択ができない自分がいました。
こんな感覚は高校生以来だ・・・ということに驚きながら、社会人になってからは「付き合い」「機会損失をしたくない」という理由で多くの飲み会やイベントに、選択せずに参加していたことにも気づきました。
よく観察していると、参加していない子は結構な割合でいました。図書室で本を読んでいたり、自分の部屋で映画を見ていたり、陶芸ルームで夜通し創作したり。
その中には全体の催しごとに総じて積極的ではない子もいましたが、多くは自分がパーティーに参加するよりも没頭できることや好きなこと、に時間を割いている印象でした。
「全体で行うこと」に参加するかどうかは自分が決め、先生も含めた周りもその決定を尊重するというのは、色々な場面で見られました。もちろん授業に全く出席しない、ということに対して、時に先生は働きかけます。
しかし、「授業に出ない」という自己決定に理由があり、その選択がその子のホイスコーレ生活において重要である場合、その決定は受けとめられていました。
自分を保つことと協調性のバランス
これらのことは、自分を保つことと周囲との協調性のバランスを試す場面であったと思います。
私がかつて感じていた「その時に自分が担っていた役割や周囲からの期待に自分が侵食されそうになっていた感覚」はまさに、 ”自分に焦点を充てた自己決定” が抜けていたように思います。
それは、”周囲に心地よくなってもらおう” ”自分の今後のためにどの選択がいいのか”という「頭」で考える決定ではなく、今どのように時間を使うことが自分の体や心にとって心地いいのか。その「今」に耳を傾けた自己決定のように感じます。
ホイスコーレの先生たちは、” Stay yourself ” “ Listen yourself ”とよく口にしました。今自分の体が感じていること、今自分の心が受け止めていること、今自分の頭が考えていること。それらに耳を傾けていると、自ずと様々なことに気づくようになりました。
自分に焦点を当てるという行為を通じて、私は次第に今目の前の相手に全身全霊で向き合うということも次第にわかるようになってきたのです。それは、頭ではなく体でできてきたと言ったほうがいいかもしれません。その過程はうまく言葉にできない、とても不思議な感覚でした。
Democracy -話したい人が全員発言する
ホイスコーレには、Living Groupと呼ばれるグループがあります。これは、授業選択とは全くことなる区分で分けられており、私の学校ではデンマーク人(もしくはデンマーク語を話す人)グループが3つ、留学生のグループが1つという計4つありました。
毎週1時間半ほどこのグループで集まり、共同生活を行う上で改善していきたいことや先生や学校に対する要望を議論もする小さな生徒会のようなものでした。
特に議題のない場合は、そのグループで散歩をしたり、歌を歌ったり、お茶をしたり、と授業とは異なったメンバーの親交を深める時間でもありました。
デンマーク特有の話し合いのやり方に、発言する時は人差し指を伸ばして挙げるというものがあります。私が最初面白く感じたのは、誰かが発言している最中であっても、その人差し指は挙げ続けたり、発言の途中で挙げたりするのです。
発言の途中で誰かが手を挙げても、その時発言している人が意見を切り上げたり、急いで喋ったりはしません。発言者が意見を言い終えるまで、周囲は耳を傾けます。そして次の発言者にバトンが渡されるのです。
民主主義の土壌
日本だと終わりの時間などを気にして、残り時間が少ない時は意見を言うのを差し控える場合もあります。デンマークでは意見を言い足りない人はどれだけ残り時間が少なくても人差し指を挙げ続けることもしばしば。
もちろんタイムスケジュールの関係で、挙手している人全員が発言できない場面もあったのですが、発言したいという気持ちのある人が可視化されたその状態はとても興味深い光景でした。
その時意見を持っている人がきちんと意見が言えるようにする。その空気感は思っていること、考えていることを言葉にして外に出すことを後押ししてくれました。
こういったDisucassion(議論)やDialog(対話)という場はホイスコーレの生活の中でしばしば取り入れられました。
Debate(討論)のように相手を論破したり、勝ち負けが発生したりするものではなく、あるテーマに沿ってお互いの見解を共有すること、もしくはある課題に対する解決策を考えるために意見やアイディアを持ち寄って、混ぜ合わせて考えること。そしてそのような場がうまく機能するには、お互いに対する信頼が根底にあって、成り立っていくのだということを、時間が経つにつれて感じることができました。

そのような場が日常となる中で、なぜデンマークでは投票率が高いのか、民主主義が浸透した国と呼ばれるのか、が次第に分かってきました。
彼らにとって、他者と共に生きることと自分を知ることは繋がっているのです。誰かと共に生きること、それは自分がコミュニティに所属し、そこで自分をどう活かし暮らしていくかということ。
自分を活かして暮らしていくには、自然と自分の強みと弱みを知ることが必要になってきます。自分ができないことをできる他の人と、一緒に物事を進めていく。その上で、話すこと、聞くことは欠かせない時間になります。
そして、自分たちがどのようなコミュニティ、社会で生きていきたいのか。それを実現していくために、政治に関わること、投票に行くこと、が不可欠となってくるのです。
自分ひとりでは完結できないようにできている
誰かを必要とし繋がっていくには、自分に足りない方がうまくいく、ということを、私はホイスコーレの生活を通じて知りました。
私の英語を補完するように、私の言いたいことをフランス人のClaire(クレア)が英語で整理し、西洋哲学の視点からの幸福観の説明も付け加えて、朝礼の準備を一緒に進めてくれました。
幸福観についてみんなで考えるという内容の朝礼は、私がなぜホイスコーレに来たのか、を説明すると同時に、私が今後日本でホイスコーレをつくりたい、という想いを伝えました。
私は同級生の中でも年齢は高い方でしたが、抜けているところも多かったため、みんなからは、「陽子はまた~~」といじられることもよくありました。
日本にいた頃は、しっかりしている、と見られたいし、仕事ができる自分で居たかった私。けれども、仕事も、地位も、未来も、なにもない状態でも、今私はみんなに助けてもらえる。
私は、完璧じゃない。今までは自分に備わっていないことばかりに目がいき、それに劣等感を抱えていたのが嘘なぐらい、私は穴だらけの自分を愛しいと思えるようになっていたのでした。
最終回は卒業が近づくにつれて生まれて始めて味わった感覚、そして私がデンマークでの生活を経てこれから思い描いていること、について書きます。